こんにちは、平林です。先日、佐賀県での教員研修があり、せっかく九州に行くので、糸島で放課後デイサービスなどさまざまな事業をされている「NPO法人 ゆめふうせん」さんを訪問し、理事長の平岡安美さんとお会いしてきました。
NPO法人 ゆめふうせん(福岡県糸島市)
[株式会社おめめどう]の人権に基づく考え方や支援グッズを活用し、視覚的支援を徹底して行う放課後等デイサービス事業等を行うNPO法人。フリースクール・通信制高校・自立訓練など事業を多方面に展開。(写真左が平岡さん、右が平林)平岡さんにお会いしたのは、昨年のおめめどう20周年イベントに飯野さんと一緒に登壇させてもらったときの懇親会でした。同じテーブルの向かいに座っておられ、Facebookでつながり、Facebookで日々の活動を拝見するなかで、ゆめふうせんで子どもたちが過ごす様子を知り、「あー、ここは子ども真ん中の活動されているんだな。行ってみたいな。」と思っておりました。
レンタカーで訪問先の周辺をうろうろとドライブするのがわたしの出張の楽しみで、今回も佐賀県で研修をした後に、大分県の日田市の宿に泊まり、翌日に、寄り道して阿蘇山を横目に通過して(全く別方向なのですが)、福岡県糸島市に移動しました。
ゆめふうせんを訪問して、一番おどろいたのが、フリースクールに放課後デイサービス、障害のある方も入居しやすいアパート、通信制高校、自立訓練など、その事業がどんどん横に展開し、そこにいろいろな人が集まってコミュニティを作っているということでした。概要を説明いただたときに「ゆめふうせん通りと呼ばれているんです」と言っていた意味が、全体を見たときによくわかりました。そして、これら全てに共通していたのが、そこに参加するひとが共有できるように情報を提示し、伝え合うという理念でした。
ゆめふうせんは法人理念には人権尊重が掲げられ、支援方針には「(株)おめめどう」の考え方と支援グッズを活用し、時間軸・予算軸・空間がわかりやすくなる手立てを行うこと基本にされています。その理念や方針をそこに参加する子どもと大人、全員が共有し、協働するために、環境の中に具体的工夫を組み込み、日々実践を続けていく。その蓄積がゆめふうせん通りという形で具体化しているんだなと思いました。
さまざまに異なっているメンバーが共に場を共有する際には、ルールも必要になる。そのルールがなぜあるのか、その理由をそこに参加するメンバーがわかる形で伝え、そのルールのある場に参加するかは、自分で決める。そして、その場をどのようにしていくかを決める場にも、メンバーが共有できる形で情報があり、自身も参加できるようにする。


こうした在り方は、子どもたちが過ごす場を支えるスタッフにも必要なことだと考える平岡さんは、例えば、キッチンの棚の中にものが戻っていないとき、それをスタッフがきちんと片付けていないとしてしまうのではなく、片付ける場所が共有しにくいのだと考え、キッチンの扉に片付いた状態の写真を貼ったり、入れるものを示したりしたそうです(視覚的構造化という方法です)。これを経験したスタッフが、今度は自分で別の場所にも写真を貼り、構造化をしていってくれていて、必要なところに広がっていく。それがとても嬉しいし、ありがたいと思っている平岡さんは、何かお菓子とかお土産をいただいたら、まずスタッフに渡すのだとおっしゃっていました。


ゆめふうせんに来ると、子どもが不思議に落ち着いて、自分のスケジュールを自分で決めて思い思いに過ごすようになり、やがて卒業していくそうです。
私は大学で「インクルーシブな地域形成事業」という名前のプロジェクトに関わっているのですが、インクルーシブな地域形成の一つの在り方が、ゆめふうせんにあるのだなと感じました。
日々、積み上げられている素敵な取り組みを、参考にしながら、自分も毎日を積み重ねていきたいと思います。
それでは、また。
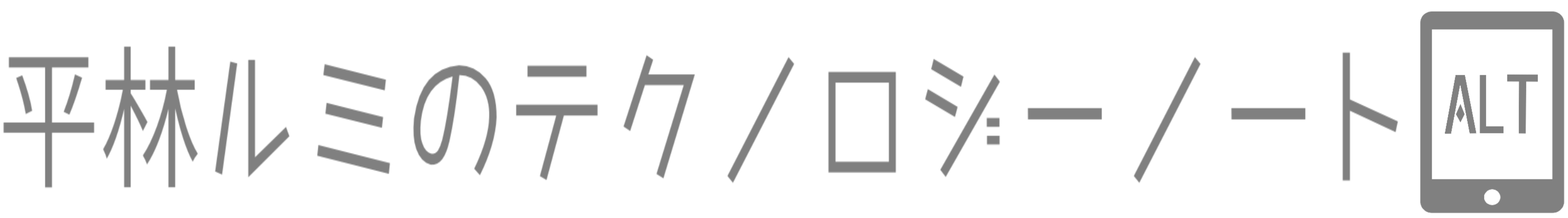




コメントを投稿するにはログインしてください。