こんにちは、平林です。子どもの権利から考える合理的配慮の研究(科研研究)が2年目となりました。昨年度(2024年)の活動を思い起こしながら、今年度もがんばります。
昨年度の4月から子どもの権利に関して、いろいろと本を読んだり、調べたりする中で、堀正嗣さんと原田綾子さんという2人の研究者に出会いました。本で出会い、リアルでも意見交換する機会をいただきました!

堀正嗣『子どもアドボケイト養成講座ー子どもの声を聞き権利を守るために』明石書店、2020年
昨年度は、インクルーシブな学校づくり研究会(月に1回自治体との連携事業として実施)が4年目でした。学校をインクルーシブにしていく上では、子どもの権利という視点は欠かせないということで、子どもの権利についても取り上げることにしました。2024年は、日本が「子どもの権利条約」を批准してから30年目の年ということは、あとから知りました。研究会では、堀正嗣さんの書籍『子どもアドボケイト養成講座ー子どもの声を聞き権利を守るために』を参考図書にして、子どもの権利擁護の基礎として、第2講「子どもの権利条約と子どもアドボカシー」、第4講「子どもアドボカシーの四理念」、第5講「子どもアドボカシーの六原則」を読んできていただいて、メンバーの先生方とディスカッションする機会をもちました。
私の心に残った箇所を紹介します。
第4講 子どもアドボカシーの四理念
p49 “自分にとって「耳障りな声」「都合の悪い声」「考えに反する声」こそ、おとなは誠実に聴いて考慮し応答する義務がある…”
第5講 子どもアドボカシーの六原則
p56 “「子どもの最善の利益を考えない」という部分がアドボケイトの重要な点です。…子どもに対して情報提供はしますが、誘導は決してしません。アドボケイトは子どもの声だからです。”
そんな中、たまたま堀さんがサバティカルで東大に来ているということで紹介してもらい、お話をするなかで、この研究会のことも知っていただき、参加してくださることになりました。
子どもへの合理的配慮に関心がある方にもとてもおすすめですので、ぜひ読んでみてください。子どもアドボケイト養成講座に、わたしも通いたいと思っています。基礎講座の後に、専門別に深める専門講座も開講されるそうです。
堀さんには、2025年4月6日(日)10時から開催される学びプラネットの月一セミナーに来ていただきます!

日時:2025年4月6日10:00-12:00
開催方法:Zoomによるオンラインイベント(申込者全員にあとから配信あり、あとから申し込みあり)
参加費:3500円
申し込み:Peatixからお申し込みください >>>

原田綾子『子どもの意見表明権の保障ー家事司法システムにおける子どもの権利』信山社、2023年
昨年度の4月に大学生協の書籍部で書籍『子どもの意見表明権の保障ー家事司法システムにおける子どもの権利』に出会いました。法律の専門書コーナーに置いてあって、価格も高いので、難しいのかなと思って手に取ったのですが、立ち読みで冒頭を読んでみると、するすると心に入ってくる文章で、これなら読めそうだと購入しました。この書籍を通して、子どもの権利条約の基本的な事項、そして子どもの権利条約の元の英語の表現がどのようなものなのかということを知ることができ、法律の中での「子ども」というのがどういう扱いなのかということもよくわかりました。
子どもの権利条約は、第12条の子どもの意見表明権が有名です。意見表明権の「意見」というのは、一体なんなのかというと、「views」であるということ。原田さんは、「views」を「一人一人の子どもの視点から見た物事の見え方や考え方を表現するもの」と書かれていました。あー、なるほどそうだよね、と思いました。
また、子どもの権利条約も、それぞれの条文についての一般的意見が出されていて、この書籍では、一般的意見も紹介しながら解説しています。第12条の子どもの意見表明権の一般的意見では、(意思決定への)「参加 Participation」という実践を通じて、子どもの意見表明権の保障が目指されるということが説明されているそうです。
これも、なるほどそうだよねと思いました。「参加」をどう確保していくのかが、子どもの「意見」を知る上では、まず大事です。
昨年度11月に、原田綾子さんに大学に来ていただいて研究会を開催しました。そこには、堀さんにも参加してもらって、意見交換しました。この時のレポートを、科研研究の成果として公開できるように、今、まとめているところです。
原田綾子さんの専門は、「法社会学」という分野で、法律そのものよりも、法律が社会の中に入って行った時にどのようにそれが扱われていくのかに関心を持って研究をされているそうです。面白そうな分野があるんだと、初めて知りました。
障害者権利条約と子どもの権利条約の違いなどもディスカッションがあって、このブログではうまくまとめて書くことはできませんが、子どもの権利擁護の活動に、障害者運動が取り組んできたことをしっかり取り込んでいけると、子どもの権利を守ることにつながるので、この点を今年もっと勉強していきたいと思っています。
それでは、また。
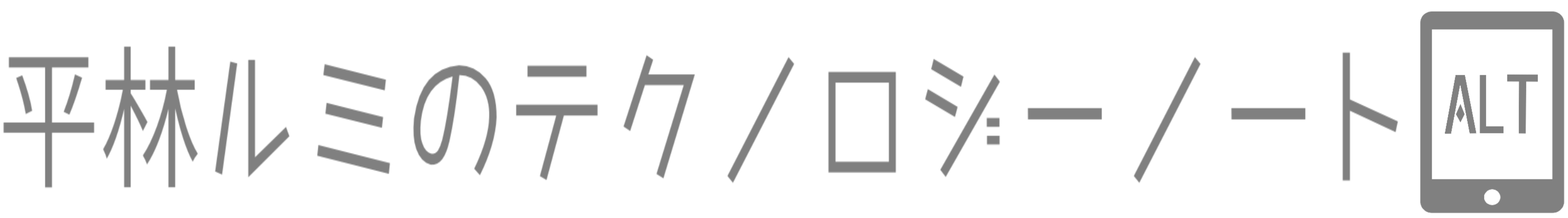



コメントを投稿するにはログインしてください。